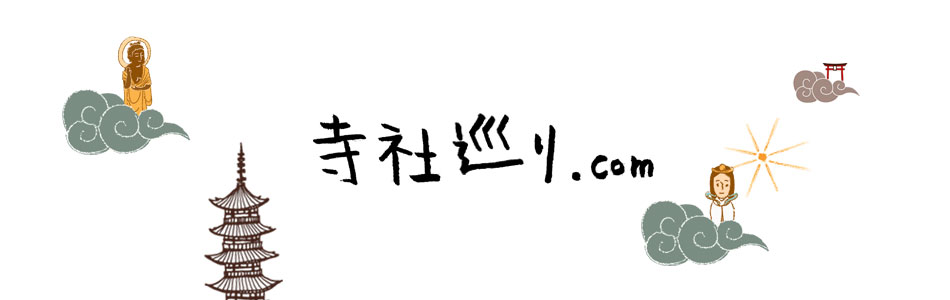お寺に行くと、お供えするローソクや線香と一緒に護摩木が置かれている場合があります。
名前や年齢、祈願したいことを書いてお寺に納めるのですが、そのあとどうなるのでしょうか?
護摩は天への供物
「護摩」というのは、サンスクリット語の「ホーマ」を音写したもので、「物を焼く」という意味です。
物を焼くと、炎があがりますが、実はその炎が重要なんです。
燃え上がる炎は「天の口」であって仏の智慧の象徴でもあり、その口から供物を食します。
つまり納めた護摩木は、供物として焼かれるのです。
そして、煙が天に届くことで、天は食を頂くことができ、代わりに人に福を与えるとされています。
このような考え方、由来はバラモン教にあります。
バラモン教が儀式で行っていたやり方を、大乗仏教も取り入れたんです。
今では主に天台宗や真言宗など、密教系の仏教宗派が護摩行(
やり方は宗派によって違いますが、主に寺院内の護摩堂というお堂の中に護摩壇を用意し、そこに護摩木を投げ入れて、焚き続けます。
また、修験道においては、護摩堂内ではなく、野外で護摩法要を行います。
下の写真のように、山伏達が火の中に、お寺に納められたお護摩をどんどん投げ入れます。


一般に、「お火焚き」や「火祭り」という呼び方で行われているお寺の行事は、この護摩供のことだと思って良いと思います。
基本的にお寺の行事ですが、神社でも明治以前の神仏習合の色が強く残っている神社では護摩供を行う場合があります。
護摩にも色々ある
護摩行は、単に護摩を火の中に投げ入れるだけではありません。
真言を唱えたり、色々な儀式の中で行います。
その方法は「大日経」という経典の「護摩盆」に四十四種類も記述されています。
祈りの目的に応じて使い分けます。
仏様も、その目的にふさわしい仏様を中心にして祈るんです。
様々な目的を、主に以下の4つに分類されます。
息災法 :地震、雷、火事、台風などの災害がないように、あるいは個人的な苦難、危険がないように祈るもの。増益法 :利益や幸福を求めるための祈願。降伏法 :魔物や怨敵を調伏したり折伏したりするために行う祈願。敬愛法 :和合や親睦をはかるための祈願。
また護摩のやり方は、実際に護摩壇で護摩木を燃やすだけにとどまりません。
自分自身の中にある煩悩を、観念的に仏の智慧を使って燃やすものも護摩行に入ります。
それを区別する場合、実際に護摩木を燃やす方法を
このように、呪術的なやり方で強い祈りの力でもって願いを叶えようというのが護摩です。